スーパーで働きつつ寿司屋を開いた男の達観
これまでにないジャンルに根を張って、長年自営で生活している人や組織を経営している人がいる。「会社員ではない」彼ら彼女らはどのように生計を立てているのか。自分で敷いたレールの上にあるマネタイズ方法が知りたい。特殊分野で自営を続けるライター・村田らむと古田雄介が神髄を紡ぐ連載の第52回。
大阪出張中に、知人から
「知り合いがやっている面白いすし屋があるので行きませんか?」
と誘われた。ちょうどお腹もすいていたので、話に乗ることにした。
1人では絶対にたどり着けない場所にある店
タクシーは「座裏」と呼ばれる地域に停まった。かつて「新歌舞伎座」(大阪市天王寺区上本町)があった場所の裏手だから、座裏という名称のようだ。細い路地にたくさんの飲食店が密集している。その中でも、かなり年季の入った建物に案内された。
1階には居酒屋が入っていて、その横を通路が走っている。雑居ビルの怪しい雰囲気が漂っていた。
そのいちばん奥に『松寿し』はあった。1人では絶対にたどり着けない場所である。
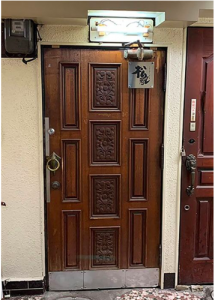
おそるおそるドアを開けて中に入ると、これまた狭い。2坪(4畳)ほどの広さであり、もちろんカウンターしかない。4人座れば満席になってしまう。
カウンターの中には、調理白衣に身を包んだ青年がいた。近藤晋太朗さん(38)だ。知人からは親しみを持って、「スシニィ」と呼ばれている。

コースはあらかじめ決まっており、飲み物の注文だけ済ませる。間もなく、目の前のお皿にスッと握りたてのおすしが1つ置かれた。
「タイの雀鮨(スズメズシ)風です」
なんのことかわからずポカンとしていると説明してくれた。
タイを酢と塩で強めに締めて、その上に煮返しを塗っている。煮返しとは酒とみりんを合わせたものからアルコールを飛ばして味を付けたものだ。その上に薄い板上の昆布が乗っている。おぼろ昆布を削りながら製作するとき、最後に残る部分だ。職人が手作業で作ったときにだけ残る食材で、今は職人が少なくなり機械で作ることが多いため手に入れるのが難しいという。タイにはすでに味が付いているので、醤油は付けずに口に運んだ。
僕の知っているおすしとはまるで違う味だったのでビックリしてしまった。もちろん美味しいのだが、それ以上にまったく知らない食べ物に触れたことが楽しかった。
それからも凝ったおすしが次々に出てくる。普通のおすし屋さんでは珍しい昆布締めにしたブリのおすし、大阪では調理に手間がかかるためあまり食べられないコハダのおすし、スルメイカを開いて干したものを水で戻し改めて煮イカにしたおすし、などなどだ。どれもとても手間がかかっているのがわかる。

続いて、煮ハマグリのおすしが出てきた。
「こちらは江戸前の仕事になります。ハマグリのおすしは大阪ではほとんど食べられないですね。生きている状態から殻をむき、その身を水から沸騰させていったん引き上げます。その煮汁に味を付けて、そこに先程の身を漬け込みます」
まずハマグリの殻を開けるのがものすごく大変だという。本には
『貝割機で開けましょう』
と簡単に書いてあるが、新鮮なハマグリはビッチリと口を閉じていてヤワな道具では開けられない。ハマグリもまさに命懸けだから必死なのだ。近藤さんはゴツいマイナスドライバーで強引に開いているという。
口に運ぶと、ハマグリの美味しさをギュウッと固めたようなおすしだった。
具材はそれほど珍しいものではなくても、手間暇をかけると未知の味になるんだと驚いた。大阪でちょっと美味しいモノ食べて帰ろう、くらいの気分だったのに、すっかりカルチャーショックを受けてしまった。
祖父も父親も修行経験はなし
スシニィこと近藤さんがどうしてこの小さいけれどすし愛にあふれるお店を始めたのか。松寿しの店内で話を聞いた。

「出身は今里新地(大阪市生野区)のど真ん中ですね。実家は祖父が開いたおすし屋さんを経営していました。僕の祖父が働いていた頃は定年が50歳だったそうで、会社を辞めた後に『さて何をしようか?』と考えておすし屋さんを始めたそうです。だからきっちりと修業をしたわけではなかったんですね」
今里新地はもともと遊郭だった地域だ。近藤さんが小さい頃はまだ色街の名残があった。
そこへ通うお客さんや、近くの工場の社長さんなどがすし屋を訪れていた。
「その後、父親が跡を継ぎました。父親は就職が決まっていたのに辞めさせられたそうです。父親も修業には行かなかったんですが、近所のおすし屋さんの技術を見て盗んで覚えたそうです」
そんな環境の中で、近藤さんは育った。
祖父の思いつきではじめたすし屋さんだから、そもそもすし屋の家系ではないのだが、なぜかいとこ3人がすし屋になっているという。不思議とすしに縁がある人生なんだな、と思う。
「小学生の時は食べることが好きだったので調理師になりたいなとは思っていましたけど、おすし屋さんとは決めていなかったですね。ケーキが好きだからケーキ屋さんになろうかな~とかふわふわした夢でした。高校の時の進路相談で『将来はすし屋になります』と言いまして、それから就職しました」
高級店で修業することになった。ただ1年間、修業はしたものの、覚悟なく入ったこともあり、あまり身に付かないまま辞めてしまった。
修業時代は人間関係で苦労することも
「そこからはお店を転々としました。いとこのおすし屋でも働きましたし、居酒屋の厨房にも入りました。
30歳になる頃に『これじゃいかん』と思いまして、職安でおすし屋さんの求人を探しました」
そして心斎橋前にある老舗店に入った。180年以上続く、総本山的なお店だった。
「最初は当時母が病気ということもあってアルバイトで入ったんですが、入店して3カ月ほどで母が亡くなってしまったので、それからきちんと就職しました」
現場はとても厳しかった。愛情はあるのだが、とにかくボロクソに怒られることも多かった。
「僕は少し集団になじめないところがあって、そこは苦労しましたね。ただ、おしさん(師匠)は怒るけど、ちゃんと教えてくれる人でした。きっちりと一から技術を学ばせてもらいました。おしさんは今でも慕って会いに行っています」
多くのすし屋は集団で働く。そこにはやはり集団ならではの人間関係の難しさはあるという。中には10年やっても出前しかさせてもらえない職人もいる。そうして不遇のまま、潰れてしまう職人も少なくないという。
近藤さんは厳しいお店で4年3カ月間働いた。近藤さんとしては、やめるつもりはなかったのだが、お店が閉店することになってしまった。
店が老朽化して建て直さなければならなくなったのだが、それに職人たちが反対し、結果的に解散という形になってしまった。職人たちは皆それぞれ新しいお店に移っていった。
「おしさんは繁華街にある大衆店に行きました。そのお店は今、外国人のお客さんがたくさん訪れていて、すしネタの回転がすごく早いんですよ。つまりすごいよいネタが使われていて、そこにおしさんみたいな一流の職人が働いてますから、オススメですね!!」
お店が閉店になったとき、近藤さんは33歳だった。それから1年間は退職金でゆっくりしながら、次の職を探した。
そして、市内の繁華街にあるすし屋さんに再就職した。
「そこが絵に描いたようなブラック企業でした。店長はオーナーに完全に洗脳されていましたね。労働時間はめちゃくちゃ法外で、店長は朝7時出勤で深夜2時までぶっ通しで働いてました。それで月給30万円ちょいですからね。狂ってます」
店長はストレスからか、空いている時間にはパチンコに通いお金を全部使ってしまうようになっていた。
「店長が途中からパチンコはやめて、貯金するようになったんです。でも自分のためにおカネを貯めてるわけじゃないんです。
『1000万円貯めたら、俺もオーナーに認めてもらえるかな?』
とか言ってるんですよ。本当に洗脳されてますね」
お店を辞め開店準備へ
労働時間が長いだけではない。失敗すると、ひどく暴力を受けた。もちろん近藤さんも、店長に負けず劣らずのひどい待遇を受けていた。
「そこで1年間働きましたけど、だんだん頭がおかしくなってきました。病院に行ったら、鬱の診断が出ました」
休養ではなく、お店を辞めることにした。
「お店を辞めるとき、つくづく僕は集団の中で働くのに向いていないんだな、と思い知りました。だったら、1人でお店を開店するしかないと覚悟を決めました」
開店資金を貯めるためにしばらくスポーツバーなどで働いた。ちょうどそのときに、父母が入れていてくれた保険が満期になり現金が戻ってきた。
「お店を開けるだけの現金が手元にできたので、場所を探すことにしました」
探していると、現在の松寿しがある場所が見つかった。元々はバーであり、前のオーナーが飛んだ(無断でいなくなった)後、1年間放置された物件だった。
物はすべて置きっぱなしで、冷蔵庫を開けると黒い液体が流れ出てきた。苦労して綺麗に掃除をし、やっとオープンにこぎつけた。
「すし職人とはなんだろうと考えました。そして“仕事をしたすし”を出すことにしました。代表的なところでは、江戸前ずしと大阪ずしですね」
僕のつたないおすしに対する認識は、「なるべく新鮮な魚を使ったおすしのほうが美味しい」
くらいのものだった。でも冷凍冷蔵技術ができたのはここ数十年の話で、おすしの歴史はもっともっと古い。
魚介類を日持ちするよう加工するのが、おすしの源流なのだ。
江戸前ずしは、江戸時代東京湾で捕れた魚を、酢や塩で締めたり、タレに漬け込んだりして、日持ちするよう工夫したすしである。
大阪ずしは、起源は平安時代まで遡る発酵ずしだ。発酵ずしでは、なれずしが代表的だ。巻きずし、バッテラずしなども、大阪ずしと呼ばれる。
どちらも現在の主流のすしではないが、大いにすし職人の腕が試されるすしである。
文献をたどり古い技術を再生させることも
「『おすしの店』にしたかったので、あてもの(おつまみ)は極力置かないことにしました。心から『すしを食べたい』と思ったとき、うちを選んでほしいですね。
今はすしバーを名乗ってますが、すし好きが集まるすしサロンにしたいと思ってます。空間を楽しんでもらいたいですね」
近藤さんは自分のことを“すしオタク”だな、と自覚している。美味しいモノには貪欲だ。
文献をたどり古い技術を再生させることもある。また、たまたま食べに行った、ミシュラン二つ星のレストランのメニューを再現する。頭の固い人には邪道と呼ばれる技法だって、美味しければドンドン取り入れていきたい。世界各国の食材加工の技術(たとえば鶏をヨーグルトに漬け込んだタンドリーチキン)もいつかすしに応用できると思っている。
「夢は大きかったですが、いきなりすし屋の収入だけで運営していくのは厳しいですから、お昼はスーパーで働きました。当初はお昼の稼ぎで家賃を払っていました」
“丁寧に仕事をしたすし”を提供するということは、つまり作業時間が長くかかるということだ。スーパーで働きながら、すし屋をするのはとても大変だった。
「朝8時に起きて市場に行きます。買った魚はいったんバイト先のスーパーの冷蔵庫にしまって、それからはスーパーの仕事をします」
松寿しは狭いため店内で仕込み作業ができない。14~15時に仕事を終えて、実家のすし屋へネタを持っていき、そこで急いで仕込みをする。お米も炊く。
「ここ(松寿し)で仕込みをしたほうが効率がいいのはわかっているんですけどね。こればっかりは仕方がないです」
仕事をしたネタやシャリを持ってお店に向かい、19時にお店をオープンしていた。
そんな忙しい日々を送っていたが、同時にお客さんを呼び込む努力もしていた。
「知り合いのバーで開催したすしイベントに参加しました。サービス価格でまずは皆さんに僕のすしを食べてもらって、自分の腕を見てもらいました。
すし屋をオープンして、友達が食べに来てくれるか? というとそんなことは全然ないんですよ。腕の保証がないと、友達だって来てもらえません。そうやって、食べていただいて自分の腕を知ってもらいました」
そして2018年7月、働いていたスーパーが閉店になってしまった。
「じゃあもうすし屋一本でやっていこうと思いました。オープンを18時に変更しました。仕込みにも時間をかけられるようになって、より精度が高くなりました」
口コミで客も増え、すし屋一本でも営業していくことができるようになった。
そしてあっと言う間に、開店して1年が経った。
いいと思った店はみんなに紹介してほしい
開店から3カ月ほどで閉店してしまう飲食店は少なくない。
「この1年はとても面白い1年でした。でもここからが本当の勝負だと思います。
とにかくここで最低5年はお店をやろうと思ってます。5年頑張って、移転の費用も稼げないなら、それまでかなとも思います。軌道に乗ったらここを拡張するかもしれないし、新しいお店に移転するかもしれません。頑張って費用を貯められるだけの実力をつけたいですね」
近藤さんは笑顔で言った。
コースの最後は、アマダイの味噌漬けのあぶりのおすしだった。店内で豪快にバーナーの炎であぶる。香ばしい臭いが店内に広がる。

このおすしは近藤さんのオリジナルメニューだという。
「カラスミを味噌漬けにするときの味噌が余ったんです。それでどうしようかなと思って。昆布締めと同じ発想でいけるんじゃないかな?と思いつきました」
昆布締めは、食材に昆布を巻くことで水分が昆布に吸収されて身が締まる、それと同時に昆布の旨味が食材に移り美味しくなるという原理だ。
味噌には塩分が入っているので味噌漬けにすると浸透圧で水分が抜ける。そして水分が抜けたところに味噌の旨味が入っていく。味噌の旨味が入ったアマダイを炙ることで、さらに旨味も出て風味も出る。
頬張ると、味噌と魚の香りが口中いっぱいに広がった。噛めば身からグッと味が出る。なんとも美味い。
こういう隠れ家的なお店は、逆に人に紹介したくなくなる。自分だけの店にして、とっておきの接客のときなどに使いたい。
そう言うと、近藤さんは笑いながら
「人に紹介したくないと思われているお店が、そのまま潰れてしまうことって実はよくあるんですよ。いいと思った店はみんなに紹介してください。それがいちばんです」
と語った。
たしかに潰れてしまっては元も子もない。皆さんももし自分だけの美味しいお店を知っていたら、そっと教えてほしい。
出典:東洋経済online


